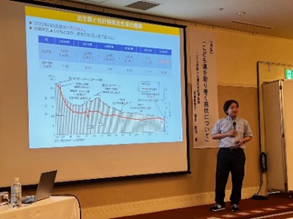テーマ:「こころの自立と実親交流のあり方」
こども家庭庁 支援局家庭福祉課 企画調整官 胡内敦司氏の発表から

妊娠期および子育て支援の重要性
妊娠期から子育てに至るまでの過程で、特に支援が必要な状況があります。計画していない妊娠や犯罪による妊娠など、これらは妊婦健診を受けないことにつながる場合があります。妊婦健診を受けない理由として、妊娠届が提出されておらず、母子手帳や健診券を受け取っていない可能性があります。このため、行政や医療機関が妊婦の存在を把握できないことが課題です。また、妊婦健診の途中で通院をやめてしまうケースもあり、これにより妊婦と胎児のリスクが高まる可能性があります。医療機関のスタッフが最初に気づくことが多く、彼らが異変を関係機関と共有し、地域全体で支援する体制が必要です。
児童福祉法では、特定妊婦として支援が必要な妊婦を定義しており、年齢に関係なく包括的な支援が求められています。子育て支援は妊娠段階から始まり、妊娠中のサポートがその後の子育ての基盤となることが強調されています。
子どもの貧困とひとり親家庭の課題
相対的貧困率の現状
最近のデータによると、子どもの相対的貧困率は14%から11.5%に改善されました。しかし、ひとり親世帯の貧困率は依然として高く、44.5%に達しています。これは2世帯に1世帯が貧困状態にあることを意味します。
ひとり親家庭の現状
ひとり親家庭、特に母子家庭は約120万世帯存在します。多くの母親が働いていますが、正規雇用ではなくパートやアルバイトが主であり、経済的に厳しい状況です。これが原因で、時間と収入のバランスを取るのが難しく、子どもと過ごす時間が制限されることがあります。
ヤングケアラーの問題
ヤングケアラーとは、家族の世話を主に担っている子どもたちのことです。彼らはしばしば、自分より若い兄弟の世話をする責任を負っています。このケアは頻度が高く、責任も重いため、彼ら自身の生活や成長に影響を及ぼす可能性があります。
支援の必要性
ひとり親家庭やヤングケアラーを支援するためには、安心して働ける環境や子どもを安心して預けられる仕組みが必要です。福祉、医療、教育などの分野で連携し、適切なサポートを提供することが求められています。
社会的養護とファミリーホームの役割
ファミリーホームは、虐待や貧困等さまざまな背景を持つ子どもたちを受け入れています。障がいがある子どもたちの割合も高く、個別対応が求められています。地域社会と連携し、子どもたちや実親も含めたその家庭を支える取り組みが重要です。
事例発表から
実親との面会方法
実親との面会はさまざまな方法でしています。児童相談所や自宅、またはホームでの面会を通じて、親子の関係を支援しています。親がリラックスして話せるよう、児童相談所の担当者がいない状況での交流も重要であると考えています。
信頼関係の構築
私たちは親ではなく、親に代わって子どもを預かる立場として、親との信頼関係を築くことを大切にしています。親が抱える不安や困難を共有し、適切な支援を提供することで、子どもたちが家庭に戻った後もサポートを続けています。
子どもの最善の利益
子どもの幸せだけでなく親の幸せも考える。親子が互いを理解し、関係を再構築するために時間をかけることが重要です。
まとめ
実親との交流は重要であり、子どもたちが親を理解するための時間と環境を提供することが必要です。親子の幸せを目指し、定期的な面会や行事への参加を通じて、実親と子どもたちの関係を再構築することを目指しています。これからも資質向上と愛情を持って、地域や児童相談所と協力しながら活動を続けていきます。
事例発表から2
実親との交流の重要性
里親やファミリーホームにとって、実親との交流は子どもの精神的安定に寄与する重要な要素です。実親と子どもの関係を適切に調整することで、子どもが成長する過程において、自分のルーツを理解する助けとなります。実親との関係が整理されることで、子どもはより安定した生活を送ることができます。
児童相談所の役割
児童相談所は、実親と里親の交流において重要な役割を果たします。交流が適切に行われるように、児童相談所が間に入ることで、子どもが安全かつ安心して実親と会うことができる環境を整えます。ただし、児童相談所の方針や支援内容によって、交流の形態が異なる場合があります。
実親との交流における課題
実親との交流はさまざまな課題が存在します。交流がうまくいかない場合や、実親の意向と子どもの希望が食い違う場合、里親や児童相談所がその調整に苦労することがあります。また、実親が突然訪問してくる場合や、子どもが勝手に実親のもとへ行ってしまうこともあり、そうした状況にも適切に対応する必要があります。
実親との交流はときに難しく、児相の協力が必要です。措置解除後の実親との交流も現実には多く、ファミリーホームの強みとして信頼を築くために、実親対応の重要性が増しています。
まとめ
実親との交流は、子どもにとっても里親にとっても重要な要素です。交流を通じて、子どもは自身の歴史やルーツを理解し、精神的な安定を得ることができます。児童相談所や地域の支援機関と連携しながら家庭復帰を目指す交流が望まれます。