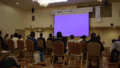テーマ:「教えて!こんな時どうする愛着障害」
~愛着障害の視点から理解する支援課題と支援の実際~
事例発表から
・愛着障害障害という言葉で一括りにしてしまうと、その子どもの特徴があるので、言葉だけで動くことは非常に難しい。その子たちがどのような背景、どのように生まれてどのような対応をとられてきたのかを第一に考えながら養育に携わってきました。
愛着というのは、膨大な領域があって、体験してきたところでは言葉だけでなく、その子どもから学び受けていきながら、どう解決していくのかをひとつずつ私なりに子どもと関わってきました。その関わりのなかで次のようなことが見えてきました。
- 子どもはお腹の中にいる間に何らかの特質を持って生まれてくる
- お腹の中にいるときからお母さん、お父さんの愛情を受けてきたのか
- 生まれた後、愛情をかけられたかどうか
そこから特徴が枝分かれしていく。

・胎内虐待があった子ども
お腹にいるときから愛情を受けていない子、生まれてからも体が硬直しています。手も足も開こうとしない、服も着替えさせられない、ミルクを飲ませるのも難しい状態。関わりのなかで、子ども同士だと安心することがわかりました。子どもに協力してもらい、体を預けてミルクを飲ませたりすると、その子はすぐに「安心・安全」を確認できました。そうすると、パーっと心も目も広がってきて周りの状況を受け入れるようになりました。
・両親からもらったもの
しっかりと愛情をかけて子どもは天真爛漫に育っていきます。だんだんと親の性格も出始めてきます。親の性格というのは、運動系・文系の子ども、いろいろなその子の特徴が出てきます。子どもの育成を考えたときに、子どもひとりひとりの特徴に合わせた形が一番大切だと思いながらそうやってきました。
・おんぶで育てる
生まれたての赤ちゃんで親御さんと別れなくてはならない子どもたち、おんぶを大切にして育てました。おんぶは赤ちゃんの呼吸音、心臓の音も聞こえるし、私の行動も赤ちゃんに伝わる。そのようなことをしていると、赤ちゃんが自然に安心になって、「自分」を出します。「教えよう」と思うと、絶対反発されるので、もう暴れようが何しようがその子の特徴なので、それも受け入れる。胎内虐待を受けた子どもは生まれたときからよく泣きます。愛情を持って生まれてきた子どもは手がかからないですね。誰にでも「嫌」と言う子どもには育たない。そんなことが私の体験としてあります。
事例発表から2
・子どもの状況
- 自分の思い通りでないと癇癪を起こす、40分でも50分でも泣き続ける。
- オムツは変えさせてくれない。排泄があっても泣かない、気にしない。
- 偏食、特定の飲み物、食べ物しか食べられない。
- スキンシップも拒否、抱かれるのが怖い、人が近くに来るのが怖い。
・心を育てる
さまざまな家庭環境により、「心が育つことができなかった子ども」、言葉が出ることも大事、いろいろと学習することも大事であるけれども、「心を育てたい」と思い、その子と関わってきました。心が育たないと、意欲とかつながりたいという気持ちが出てこない。そうするとやっぱり幸せになることが難しいです。
・入口と出口の支援
朝起きたとき、「おはよう」と言って、「今日も1日、一緒にいっぱいいろんなことをして楽しもうね」「こんなこと一緒にできるのはすごく楽しみだよ、嬉しいね」ということを伝えます。外出して帰ってきたときには、「えー○○先生とこんなことしたの?めっちゃ楽しかったね、良かったね、にこにこ顔で帰って来てくれて嬉しいよ」といったことを私や家族がしています。また、感情を爆発させて、だから言うことを聞くことは一切しない、こともしています。
・安心、安全
抱かれるのが怖いから、スキンシップも最初は拒否でした。でも後ろから毛布みたいにふわんとかけてあげると、嬉しそうに丸くなるので、その上からとんとんってしながら、今はもう反対に後ろからスリスリしてきたり、手をギュッとしてしがみついてきたりできるようになりました。本当に安心・安全、そばにいて心地よい、人に寄りかかって寝ることがだんだんとできるようになりました。
・食の広がり
食の広がりは心の広がりだと思っています。食って自分でコントロールができるので、安心できていなかったら、勧められても食べられないですよね。食が広がっていくと、「この子本当に安心できたんだな」ということをとても感じます。
・親支援も含めて
「子育ての仕方がわからない」ということで、支援しながら子どもと交流をしながら、相談を受けながら、いずれは親のもとに戻れるように、できるだけ親から愛されるように、親も疲弊してしまわないようにできる限りのことをしたいと思っています。