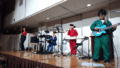テーマ:「家庭養護における家庭支援のあり方」
~支えよう!守ろう!『この子』の家庭~
栃木フォスタリングセンターについて
栃木フォスタリングセンターはオープンして約3年となりました。栃木県からの業務委託を受け、フォスタリングパートナーとして、経験豊かな里親さんや保健師さん、元施設職員の方、里親支援専門相談員、児童福祉司さんとともに里親の相談業務や訪問業務を担っています。
業務内容としては、相談訪問の他、普及啓発、広報、研修、子どものみが参加する自然体験宿泊プログラムなど、さまざまな工夫を凝らしながら行っているところです。
課題としては、TFCがまだ知られていないこと、里親制度を理解しても里親を知るところまではなかなかいかないこと、権利擁護も進んでいくなかでみんなで意識していくべきということ。課題は山積みだなと思っております。
今年度、里親支援センターについて、栃木県がどのように動いていくのか、オール栃木という体制の中から今の形ができてきたので、今後どのようにしていくのかに、真剣に向き合わなければならないと思っております。
静岡市の取り組み、設立の経緯と今後の展望
静岡市は、19年前に政令市に移行し、静岡市児童相談所が設置されました。当時、静岡市里親会の初代会長は、元児相長でもあり、里親がまず「自ら動こう」と打ち出し、静岡市里親会は平成22年にNPO法人となり、平成23年に市からの委託で相談活動と研修の事業を行うことになりました。当初は、里親会の役員さん2人と、里親委託促進事業を担う推進員さんたちだけでその業務を行っていました。
その成果が認められ、平成25年には里親支援業務全般を委託されることになり、市の里親支援の非常勤の職員がそのままNPOの方に入り、里親支援業務を続けることになりました。コツコツと心をこめて堅実に里親さん、関係者と信頼関係を構築してきました。平成30年にフォスタリング機関として位置づけられ、令和6年4月には、里親センターとして始動することができました。
静岡市は委託率の高さでは毎年上位に位置しています。また不調による措置変更も少ないです。里親申請希望のときから、里親養育の十分な説明を行い、希望者の方がどのような方であるのか何度も訪問したり、研修や体験を重ねていただきながら、すぐに子どもを受託できる環境が整ったところで里親登録が完了するようになっています。
里親の養育研修は、その家庭に合わせてピンポイントで研修の案内をし、必要な研修を受けていただくようにしています。里親会と共同で行う夏キャンプでは、夜には大人と子どもにわ
かれてサロンを行い、子どもたちの声を出せる機会も作っています。
里親養育支援が児相から離れて11年経ちました。そのなかで感じているメリットとして民間であるっていう強みを生かして、想像力を豊かに自由な発想を展開しています。
北海道における現状
北海道は14の振興局が行政単位となっています。担当となっている所は、端から端まで車で8時間程かかります。そのような土地柄で活動をしております。この地域にファミリーホームは一か所しかありませんが、どこに行くにも時間がかかる地域なので孤立しやすく、児童相談所に相談しにくい現状がありました。
大変な養育をどこにも相談できずに困っておられ、児相もベテランの養育者の方なので、その困り感に気づいていなかったこともありました。私は児童養護施設の職員として子どもの養育に携わってきたなかで、同じような経験をしてきたので、児相と里親さんの間に入り、里親さんが困っていてこのままでは危険も生じるということを児相に伝えることができました。
里親支援専門相談員は、施設のシフトに入らず業務を行うことになっており、それができるおかげで、広域性の特色ある地域でも訪問にも力を入れられますし、支援の継続性という点では大きなアドバンテージになっていると思っています。
今困っていることは、広域性が持つ問題、すぐに対応できない、その場にたどり着くまで時間がかかることです。その対応策として、専用スマホでLINEでつながり、通話やLINEで何とか対処していますが、さらに良い対応方法を考えていきたいと思っています。
パネルディスカッション
コーディネーター
・元厚生労働省雇用均等児童家庭局家庭福祉課長
全国家庭養護推進ネットワーク代表幹事 東京都里親 藤井康弘氏
パネラー
・北海道庁子ども政策局 ・北海道中央児童相談所 ・札幌市児童相談所
・社会福祉法人養徳園 福田総合施設長 ・栃木フォスタリングセンター
・静岡市里親家庭支援センター ・里親支援専門相談員
・こども家庭庁支援局家庭福祉課 福永児童福祉専門官

まずは北海道の行政の方から北海道、札幌市のこれまでの取り組みと合わせて、先程の3名の方のお話を踏まえて、どんな感想をお持ちかお話をいただければと思います。
北海道には児童相談所は8つあります。里親登録数は605人、札幌市が411人、合わせて1016人の登録があります。そのなかで554人が養育里親です。北海道は一つの児相の管轄の範囲がとても広く、広域性という特色があります。それぞれの児相に里親会があり、14ある振興局には施設の里親専門相談員さんがいるという状況になります。里親さんは、50代60代の方が60%以上で高齢化も進んでいますが、委託率は36%と全国平均より高くなっています。里親支援センターの設置について、北海道の方でも検討しているところであり、今日のお話が聞けて良かったなと感じています。
北海道はフォスタリング機関は児相が担う形になっています。北海道はまだまだ体制が整っておらず、広域性の問題で、家庭訪問に行くにも片道2、3時間というのが普通のなか、里親担当の福祉司と施設の里専さんの協力を得て支援しているという形です。今後里親支援センターができていくことで、民間の力を活用し、行政では手の届きにくい里親さんの望むサービスを届けていけるような研究をしていければと思っています。
札幌市は、民間の3か所のフォスタリング機関に委託しています。札幌市では、機能別でフォスタリング機関にお願いしているという特徴があります。児童養護施設を母体、乳児院を母体とするフォスタリングでは、それぞれのお子さんに合わせた支援を行う狙いがあります。また障がい児のお子さんを受け入れる里親さんのリクルートと支援をお願いしているのは、麦の子会さんです。札幌市は委託率39.2%ということではありますが、静岡市のようにもっと工夫して委託率をあげていきたいなと思った次第です。
本日の栃木県と静岡市のお話を聞いて、北海道、札幌市の支援体制について、民間との役割分担や協働という部分で、もう少し子ども政策局と中央児童相談所にお話ししていただけたらと思います。
私自身は、民間主導、里親主導というのはありかと思うのですが、行政の役割として里親支援はしっかりしていかなければならないと思います。里親支援センターを立ち上げるにあたって役割分担をしながら里親さんの悩みに対応できるようにしたいと思いますが、栃木県のようにぐいぐい引っ張ってくれる人が今のところいないので、みんなで協力していくしかないと思っています。
事業をするには予算がかかるなかで、今回里親支援センターを福祉施設と位置づけられたことで各自治体も取り組みやすくなっていると思います。北海道でも児童養護施設等、民間の力を借りてフォスタリング機関や里親支援センターを増やしていかなければ、支援の手が行き届かないと思っています。
札幌市では機能別のフォスタリングとなっているとのことですが、今後里親支援センターにおいても機能別を求めるのか地域別を求めるのか、理想論を言えば、里親がフォスタリング機関を選べるような体制も展望すればいいなと思っていますが、いかがでしょうか。
私たちも非常に悩んでいるところでして、それぞれの法人の強み、専門性の部分でお願いしていきたいという思いがあります。また地域性ということでは3つでいいのかということも含めて考えていきたいのですが、現在フォスタリング機関と里親支援センターと何が違うのかということを予算要求で説明していかなければならないところに一生懸命取り組んでいます。
それぞれの登壇者のみなさんから一言ずつ助言をお願いします。
児童養護で子どもをずっと見ていてやっぱり里親の方が絶対いいなと思ってきました。しかし今子育てが大変な時代で、里親さんはとても大変だなということがわかってきました。支援する側、支援される側一緒に子どものこと考えましょうということが大切で、養育には正解がない。どんな養育のプロでもすべてうまくいくわけではない。経験者であろうと、学識者であろうと、養育が難しいのは当たり前のことというなれば、里親さんに一番大切な技量は支援を求める力だと思っています。
私は里親さんの顔が見えることが一番大切だと思っています。里親さんがつながることで子どももつながっていく。児相は異動があるけれども、顔を見て里親を知ってもらう。そしてケースを知ってもらう。会うということをいつの時代の中でも大切にしていくことが必要と感じました。
北海道は広いし、児童相談所はオーバーフローしているというところはありますが、それを乗り越えるべく顔の見える関係で関係機関のみなさんとこれからも一緒に考えていければと思います。
私自身もいろいろなお話を聞かせていただき、改めて皆様が真摯に子どもの養育に向き合われていることを実感させていただきました。心から敬意を表したいと思います。これからも児童相談所も子どもたちのために目指してるところは一緒ですので、手を取り合って進めていきたいと思っております。
私も昨日今日といろいろとお話を聞くなかで、やっぱり里親さん、ファミリーホームの養育者の方々は、子どものことをしっかりよく見ている。だからこそ不安や心配、悩みが生じてしまうということがあるのだなと改めて思いました。その悩みや不安を自分だけで抱え込んでしまわないように、相談しやすい体制や、関係作りを関係機関のみなさんと作っていかなければと思います。
北海道の広域性の話を聞いて、栃木の片道2時間なんて大変と言っていられないと思いました。もっと里親さんに近い距離で、物理的だけではなく、精神的にも近いところで里親さんを知っていきたいというのが今の実感で、早く栃木に帰って職員にもいろいろ伝えたいなと思っているところです。
私の所では、里親さんと施設は横のつながりが深く、長期休みになりますと、里親さんを中心にショートステイをお願いしていました。里親さんから退所後の子どもたちの情報を聞くこともあり、里親さんと活動を共にしてきております。支援する側、される側という立場よりは、同じ支援をする立場として里親さん、ファミリーホームの方にはいつも感謝をしています。
国というより、私の解釈の中でお話させていただきますが、フォスタリング機関はそれまで児相が担っていた部分を民間を活用して支援の場を増やしていくという狙いがあったかと思います。今後里親支援センターができていくなかで、これまでのフォスタリング機関はどうなるのか、という声も聞こえてきますが、里親支援センターは義務的経費として絶対にお金がつくところに大きな舵を切ったと思っています。同時に、フォスタリング機関をいつまで併存して残せるものかと実は国の方でも悩んでいるところです。突然なくなることにはならないと思いますが、ずっと併存というのもないと思います。できる限り里親支援センターに移行していく流れかと思います。そういう意味でも今日のお話非常に参考にさせていただきましたし、これからもこども家庭庁としていろいろ一緒に考えていきたいと思っております。
最後にまとめとして、2つ。ひとつは顔が見える関係ということ。お互いの顔が見える関係で信頼関係を築きながらつながっているということが何よりも大切だと思います。そこを担保できるような体制作りをお願いしたいと思います。
もうひとつは、予算要求のさまざまな壁があることはもっともなところですが、そろそろパラダイムシフトを起こさなければならないときだと思うのです。今回こども家庭庁では、かなり頑張ってくれています。それぞれ自治体の方でも少し通常の枠とかルールを飛び越えて、ダイナミックな予算編成をぜひ考えていただければありがたいなと思います。